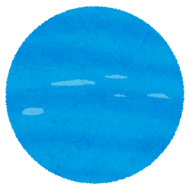今から数年前、ふと、教室に掲示してある夏合宿のポスターを見ると「北海道」の文字が目に入りました。
しばらくその文字を見ていると「あれ?北って漢字はこんな形をしてたっけ?」と思い、すぐに紙を持ってきて書いてみました。
「違う。形が違う……」目の前の紙に書いた北の形と、ポスターに書かれている北の形が違っていました。
全身から血の気が引いていくのが分かりました。小学校でこの漢字を習い、それからウン十年。漢字を間違えたまま覚えてしまっていたのか?間違いに気づかず今まで書いてきたのか?冷汗が止まりません。
急いで漢和辞典を持ってきて調べました。漢和辞典に載っているものも自分が書いていた形と違っていました。「なんてことだ……」その場に崩れ落ちそうでした。しかし、筆順のところをよく見ると、自分が書いた形と同じでした。
「間違ってはいないのか?」
その後、他の先生に「北」という字を書いてもらうと、さっき自分が書いた字と同じ形でした。そこでようやく北という文字は、「書いた形」と「印刷された形」が異なるということが分かりました。
人生で一番衝撃を受けました。
それはなぜか。今まで「北」という文字は何百、何千と見てきたはずなのに、「書いた形」と「印刷された形」が違うということに全く気づいていなかったからです。
気にも留めていなかったこと。
それが当たり前と思い、別のことを考えもしなかったこと。
身の回りにはそんなことがたくさんあるのかも知れません。
ちょっと立ち止まって、見方を変えてみると、今まで気づかなかったことに気づいたり、見ているようで見えていなかったものに出会えるかも知れませんね。
ちなみに君は「北」という漢字は「書いた形」と「印刷された形」が違うことに気づいていましたか? 日本人のうち、いったいどれくらいの人が気づいているのか?気づいていなかったのは自分だけなのか?秋の夜長に考え出すと眠れません(笑)