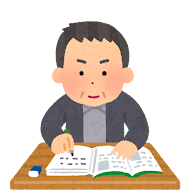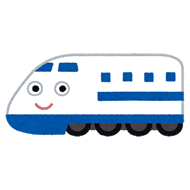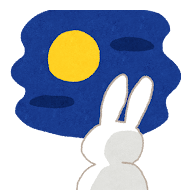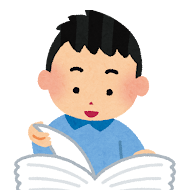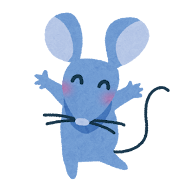
昆虫少年だった伸一君(だれだろう?)は、日々、蝶やカミキリムシの採集に夢中でした。そしてもちろん、将来は大好きな昆虫を研究して、生物学者になるつもりで大学に進学しました。
しかし、昆虫の研究の多くが「害虫」、つまり人間にとって迷惑な虫をどう駆除するかというテーマが中心。
農薬の研究なども多く、結局は大好きな昆虫を殺すための勉強ばかり。
伸一君はあっさり挫折してしまいました。
そこで、当時脚光を浴びていた「生命とは何か?」というテーマをミクロな視点で研究する分子生物学に挑戦することにしました。
厳しい研究の末、彼はついに新しい遺伝子細胞を発見!(やったね、伸一君!)
彼は、この遺伝子が生き物にどのような情報や役割を持っているかを実験で確かめることにしました。
実験方法は、発見した新しい遺伝子細胞をネズミから取り除き、その後の変化を観察する、というものです。
ネズミに何かしらの異常が現れれば、遺伝子の役割が見えてくるはずです。(すごいね、こんな方法を考え出すなんて!)
伸一君が発見したこの新しい遺伝子は「GP2」と名付けられました。
GP2を取り除いたネズミを育てるのにまず3年かかりました。(おーーー!)
その後、GP2を欠いたネズミを毎日観察。
しかし、ネズミはすくすくと健康に育ち、子どもまで生まれました。
「なんでなんだ~!」 ネズミは健康そのものです。
この頃の生物学の世界では、生物も機械のように考えられ、一つ一つの細胞もパソコンの部品のようなものと同じだと捉えられていました。
だから、どこかの部品がなくなれば当然、不調が起こり壊れてしまうはずだと考えられていたのです。
「なぜネズミは平気で元気なんだ…うーーーー?」
伸一君はまたも大きな挫折を味わいました。
けれども、彼には新たな考えが生まれました。
長い年月をかけて生き残った遺伝子細胞がなくなっても何も起こらないということは、もともとの考え方が間違っているのではないか?
そうして彼は、当時は忘れ去られていたシェーンハイマーという100年前の学者の言葉を思い出しました。
「生命は機械ではなく、流れである」という言葉を。
その後、伸一君は、生物にとって食べ物は車のガソリンのようなものではなく、体は常に自らの細胞を壊しながら、食べ物を取り込み、新しい自分を作り直していることを知りました。
すごいね。
特に新しく入れ替わるのは胃や腸などの消化器官の細胞で、早ければ1か月で入れ替わるのです。
人間全体も1年もすればほとんどが新しい細胞に入れ替わるそうです。
そして、生き物は(僕らも)何かを失っても他の部分で補い、常に細胞を入れ替えながら、絶妙なバランスを保って生き続けているのです。
これを「動的平衡」と呼ぶそうです。
昨日の自分は、厳密には今日の自分とは違うわけです。
僕らは日々自分を壊し、新しく作り替えながら生きているんだね。
すごく気持ちいい話だと思わない?みんなはどう感じるかな?
※伸一君についてもっと知りたい人は、ネットで調べてみてください。
【福岡伸一先生】