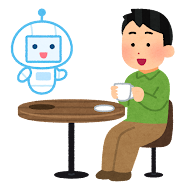あなたは生きています。
これを読んでいるのだから当然です。
では「生きる」とは何でしょうか?
●今ここに存在すること? ⇒ ふでばこや家は生きていませんね?
●動いていること? ⇒ 雲や車は生きていませんね?
この問題は非常に深く、明確な答はおそらくありません。
「生きる」とは、生物学的には【自己再生・刺激への反応・子孫を残す】こととされています。
けがをしたら生命の力で治し、外からの刺激に対応し、次の世代の生命を生み出す、ということです。
車は壊れても自分で直すことはできず、古くなって新たな車を作り出すこともできないので、生きているとは言えないのですね。
※AI搭載のロボットが「自らを直し、新たなロボットを生成する」ことができれば、生命といえるかもしれませんが…
また、哲学的には、「生きる」とは「自己選択と自己形成」とされています。
難しい言葉が出てきましたが、言い換えると
●自分で考えた自分の意思を持つこと
●自分の考えにもとづいて行動すること
●自分に良い変化をもたらすこと
が「生きること」ではないか、ということです。
「悪い点数を望む人」はほぼいません。
なぜ「よい点数を取りたい」と考えるのか?
それは「自らを良くしたい」という本能的な望みがあるからではないでしょうか。
学習においても、習い事においても、『ただやればいい』のではないと思います。
まず『どうなりたいのかを考える』こと、そしてその考えたことに対して『どうすべきか考えて実際に行動する』ことが大切なのです。
そうすれば『自分に良い変化をもたらす』ことにつながっていくことでしょう。
自然界における生命は生まれたら必ず死ぬことが運命づけられています。
何のために生まれ、何のために死ぬのか。これも明確な答はありません。
やがて死ぬのであれば何かをしても意味がないという考え方もありますが、「何もせずにただ生きている」、そういう生き方を望みますか?
自分がどうなりたいか、秋の夜長にふと考えてみてはどうでしょうか。