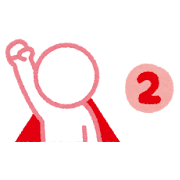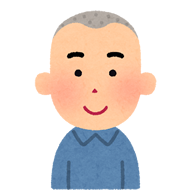「白って200色あんねん」という言葉を聞いたことがありますよね。
では、みなさんは「紫色」と言われたら、どんな紫色を思い浮かべますか?
ひとくちに紫といっても、赤に近い紫もあれば、青に近い紫もあります。
私は紫色が大好きですが、特に赤みのある紫に強くひかれます。
高貴さや華やかさ、そして前向きなエネルギーを感じる色だからです。
けれども、ネットで「理想の紫」を見つけて注文しても、届いてみたら「これは青に近いな」と感じることも少なくありません。
紫は赤と青が混ざってできる色です。
ほんの少し配合が違うだけで、印象はまったく変わってしまいます。
だからこそ、自分の好きな紫を見つけるには、何度も試し、比べ、自分の感覚と向き合うことが必要になります。
色にこだわりがある人ならきっとわかってくれるはずです!
私は、このことは勉強にもよく似ていると思っています。
同じ塾に通い、同じ授業を受け、同じ時間勉強していても、成果の出方は一人ひとり違います。
それは、理解の仕方も、集中できる時間も、得意・不得意も、それぞれ違うからです。
「勉強」とひとまとめにするのではなく、「自分にはどんなやり方が合っているのか」を考えることが大切です。
成績を伸ばすために本当に必要なのは、量だけではありません。
自分を知り、自分に合った方法を探し続ける姿勢です。
うまくいかないときもあるでしょう。不安になることもあるでしょう。
でも、そのたびにやり方を見直し、工夫し、少しずつ積み重ねていく。
その過程こそが、みなさんの力になります。
紫色も、何度も色を重ねることで、より深く、美しくなります。
努力も同じです。
すぐに結果が見えなくても、重ねた分だけ確実に自分の中に残ります。
みなさん一人ひとりが、自分だけの「色」を大切にしながら、自分に合った学び方を見つけていってほしいと願っています。