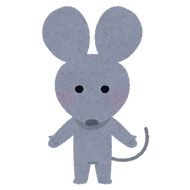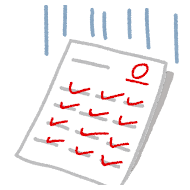今日はみなさんに、「自分をちょっとだけ最強にする方法」をお話ししようと思います。
“最強”なんて、いきなりどういうこと?
――そう思った人もいるかもしれませんね。
でもこれは、ゲームやアニメの世界だけじゃなく、現実の世界でも使える“本当に大事な力”なんです。
その方法とは――ずばり、「リフレクション(ふり返り)」です。
リフレクションとは、自分の行動や考え方を立ち止まって見つめ直し、「次はどうしよう?」と考える力のこと。
似た言葉に「反省」や「内省」もありますが、リフレクションはもっと前向きな“ふり返り”です。
「うまくいかなかった」で終わらせず、「どうすればうまくいくか?」を考える。
この姿勢こそ、自分を強くしていく第一歩なんです。
実は、人間の行動の約95%は無意識で決まると言われています。
つまり、私たちが「よし、こうしよう」と意識して決めているのは、たった5%ほど。
残りの95%は、習慣やクセ、気分、環境――“なんとなく”で動いているんです。
たとえば、朝起きてすぐスマホを見てしまう。
気づいたらゲームをしている。
なんとなく動画を見続けている……。
こうした行動は、ほとんどが無意識のパターンです。
でも、その無意識に気づかないままだと、毎日同じ行動をくり返すだけ。
だからこそ、自分の行動に光を当てて見つめ直す――それが「リフレクション」なんです。
アニメのキャラクターたちは、この力を自然に使っています。
たとえば『鬼滅の刃』の炭治郎。
彼は戦いのたびに「どうして斬れなかったのか」「どこを見落としたのか」を丁寧にふり返ります。
失敗を恐れず、次に生かす。それができるからこそ、彼はどんどん強くなっていくのです。
『ドラゴンボール』の悟空も同じです。
毎回ボコボコにされても、「オラ、次は勝つぞ!」と自分を見つめ直し、修行を重ねていきます。
負けを“終わり”ではなく“始まり”に変える――それが悟空のリフレクションです。
そして『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久(デク)。
彼は戦いのたびに自分の動きや力の使い方をノートに記録し、「次はこうしてみよう」と考え続けています。
その地道なふり返りこそ、彼をヒーローへと成長させている原動力なんです。
こうして見ると、強くなれるキャラクターはみんなリフレクション上手。
失敗しても落ち込むだけで終わらず、そこから学び、次につなげる。
リフレクションは、彼らの“成長のエンジン”なんですね。
もちろん、これはアニメの中だけの話ではありません。
私たちの日常でも同じです。
テストで思ったより点数が低かったとき、「もっと勉強しとけばよかった〜」で終わらせるのではなく、「どこでつまずいたのか」「どんな準備をすればよかったのか」と考える。
それだけで、次のテストで点数を上げるヒントが見えてきます。
友達とケンカしたときも、「あいつが悪い!」で終わらせず、「自分の言い方を少し変えたらどうだったかな?」と考えることで、次はもっと良い関係を築けるようになります。
気づいたらスマホやゲームに何時間も使っていた日も同じ。
「なぜそうなったのか」「何を変えれば10%だけ改善できるか」と自分に問いかけるだけで、明日の過ごし方はきっと変わっていきます。
もう一度、最初の話に戻りましょう。
人は95%の行動を無意識でしている。
でも、リフレクションをすることで、自分の“無意識のクセ”に気づけるようになります。
そうすれば、「じゃあ、こう変えてみよう」と意識的に行動を選べるようになる。
それこそが、意識を成長させる第一歩なんです。
そこで、みなさんにちょっとしたチャレンジを提案します。
それは、「1日1リフレクションチャレンジ」です。
夜寝る前やお風呂に入っているとき、たった1分でいいので、自分に問いかけてみてください。
・今日、うまくいったことは? うまくいったのは何があったからだろう?
・うまくいかなかったことは? どうすれば前より少し変化がうまれるだろう?
この小さな習慣を続けるだけで、自分の中の“無意識”が少しずつ“意識”に変わっていきます。
そして、炭治郎のように、昨日の自分より少しだけ強い自分に出会えるようになるはずです。
どんなにすごいキャラクターでも、最初から最強だったわけではありません。
彼らは「リフレクション」をくり返すことで、確実に強くなっていきました。
そして、その力は――みんなの中にも、ちゃんとあります。
「ふり返る」という小さな習慣が、未来の大きな成長につながります。
今日も明日も、その先も。
ちょっとだけ自分と向き合い、自分だけの“最強”を目指していきましょう